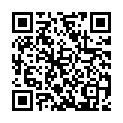Q4-3 「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言書が見つかりました。次男である私は1円ももらえないのですか?
■「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言が見つかった!
先日、父Aが亡くなり、遺言書が見つかりました。
そこには「全ての遺産を長男Cに相続させる」とあり、母Bは納得しているようです。
しかし次男である私(D)だって同じ父の子なのに、全く遺産がないというのが納得いきません。
何とか少しでも遺産をもらう方法はありませんか?
■遺留分を侵害された場合は、侵害額請求ができる
遺言書がある場合には、その内容にに従って相続するのが原則です。
法律で定めた形式に従った遺言であれば、「全ての遺産を長男に相続させる」という遺言自体は有効であって、他の相続人がそれに異論がないのであれば、そのまま進めることには何の問題もありません。
しかし相続には、遺された相続人の生活保障という側面もあるため、希望する人に確保されるある一定の割合があります。
それを「遺留分」(いりゅうぶん)と呼びます。
親から子への相続の場合、遺留分は法定相続分の2分の1です。
上記のケースでは、本来の法定相続分はBは4分の2、CD各4分の1ですので、Dの遺留分は4分の1のさらに半分の8分の1となります。
このケースではこの遺留分が侵害されているので、DはCに対し、遺留分侵害額請求をして、少なくとも8分の1に相当する分を現金で払え、と言えるのです。
■お金で解決。不動産自体は長男C名義のまま
例えば上記のケースでCが不動産を相続し、Dが遺留分侵害額請求をすると、B8分の7、DB分の1の共有持分としなければならないのでしょうか?
答えは「NO」
民法の改正により、2019年7月1日以降に発生した相続で遺留分が侵害されているケースでは、次の通りの扱いとなりました。
1.遺言によって相続した不動産自体はあくまでも遺言通り、長男C名義のまま
2.二男Dが遺留分侵害額請求を請求した場合、長男CはDに対し、侵害された遺留分に相当する金銭を支払う
この背景には、不動産のような財産を共有にすると、さまざまな不都合が発生するから、というものがあります。
ただし1点注意があります。
それはCに手持ちの現金がない場合です。
例えば遺産に預貯金がほとんどなく、Cもポケットマネーがほとんどない場合。
この場合は、すぐに侵害額を支払いできません。
この場合、分割支払、不動産を売ってその中から払う、などの対応が必要になる場合があります。
■遺留分侵害額請求は1年以内!
この遺留分侵害額請求権は、自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年で消滅時効にかかります(民法第1048条)。
また相続開始の時から10年を経過したときも同様です(同条)。
「不公平な遺言がある?」と思ったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
当事務所では、このような相談があった場合、信頼できる弁護士を紹介して対応させていただきます。
ただし上記の通り、遺留分侵害額請求の有無にかかわらず、不動産は遺言の通り所有権が移転しますので、当事務所で相続登記等の対応をさせていただきます。