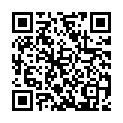Q 自筆証書遺言は全て手書きでなければいけないのですか?
■財産目録はパソコン等でOK。ただし注意点あり
これまで、自筆証書遺言は、全て手書きでなければなりませんでした。
しかし民法の改正により、財産目録の部分はパソコン等で作成してもよくなりました(民法968条2項)。
ただしいくつか注意点があります。
1.本文だけでなく、財産目録にも署名・捺印が必要
2.財産目録の署名・捺印は全てのページに必要
3.改正施行日の2019年1月19日以降に作成された自筆証書遺言に限る
(これより前に作成されたものは、従来通り全て手書きでなければ無効)

法務省パンフレット「相続に関するルールが大きく変わります」より抜粋
これにより、次のようなメリットがあります。
1.字を書くのが大変な方でも作りやすい
2.書き換えのハードルが低くなる
→家族構成や財産額・構成が流動的な若い方でも作りやすい
■要件が緩和されても専門家によるチェックは推奨
これにより、「これなら自分も作ってみよう」と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
また書店等に行けば、自分で作れる「遺言キット」も多く売られています。
ただやはり専門家としては、自分の判断だけで作成するのはお勧めしません。
仕事柄、「夫が遺言を残して亡くなったので手続をお願いします」という依頼を受けますが、専門家のチェックを受けずに作成した自筆証書遺言は、ほとんどの場合、何かしらの「残念ポイント」があります。
私が過去、実際に見た「残念な」遺言の例
1.夫婦連名で作成
→無効です(民法975条)
詳しくはこちら
2.「~に○○を贈与する」
→本来は「(相続人)に相続させる」または「(相続人以外)に遺贈する」
3.相続対象の不動産を住居表示で書いている
→本来は登記簿の通り地番や家屋番号で特定する
詳しくはこちら
4.不動産だけを遺言し、預貯金は遺言していない
→預貯金は遺言がない場合と同じく、遺産分割が必要。
他の相続人から遺産分割の協力を得ることが困難なケースでは、預貯金を下ろせない
特に注意していただきたいのは、3~4のように「無効ではないけど残念」なパターンです。
一般の方は、遺言が有効か無効かだけに意識が行きがちです。
しかし我々専門家は、有効なのは当たり前、その上で、
「手続がしやすいかどうか」
「争いを防止できるかどうか」
を重視します。
せっかくの家族への厚意が水の泡とならないよう、遺言は専門家に相談の上、文案作成を依頼することを強くお勧めします。
■将来的には全てパソコンで?
また2023年現在、全てをパソコン等で作成する「デジタル遺言」制度も検討されています。
指定のフォーマットに入力するので、形式的な部分で無効となることはなくなりそうです。
ただし偽造防止・真正担保の観点から、電子署名や証人立会、遺言時の録画必須、などの条件がつきそうです。
詳細がわからないので何とも言えませんが、自筆証書遺言がパソコンでできるようになるというより、デジタル遺言という遺言の種類が1つ増えるようなイメージで捉えた方がいいかもしれません。
そして、その取っ付きやすさ・難易度としては自筆証書遺言以上・公正証書遺言未満のように予想します。
これについては方針が政府で決まり次第、このサイトでもお知らせします。